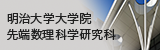所員・研究員の活動
三村昌泰MIMS所長が,沖縄県立開邦高等学校理数系講演会で現象数理学の紹介をしました。
2009年12月24日,三村昌泰MIMS所長が沖縄県立開邦高等学校理数系講演会において現象数理学の紹介をしました。
自然の中に現れる数学を探る
自然界には、今でも、我々の想像を超えた、不思議さ、神秘さ、謎が残されています。熱帯魚には大胆な模様と色の多様性、昆虫の擬態が示すように生き物の巧妙な仕組み、あるいは脳や神経を持たない単細胞の真性粘菌が示す迷路解き等例枚挙に遑がありません。我々は長い間、生物と非生物とは異なっているのではないかと信じてきました。端的な例は、生物の発生の問題でしょう。例えば、カエルの発生を考えると、球という対称性を持った受精卵の細胞分裂である卵割から始まり、細胞数は2の倍数で増えていき、やがて対称性が破れて、オタマジャクシになり、そしてカエルになります。何故丸い形の受精卵が複雑な形状を持つカエルに変化していったのでしょうか?観察から実験へと研究方法が進む中で、遺伝子がその正体であることを明らかにしたのは、1953年科学雑誌 nature に掲載された、クリックとワトソンのわずか2ページの論文です。これが契機になり、「遺伝情報を生み出す遺伝子を調べれば、生物,生命系が理解できる」という期待の中で、分子生物学、分子遺伝学と言う新しい学問分野が誕生しました。
ちょうどこの時期、1952年、イギリスの数学者であるチューリングは、「拡散は空間一様化を促進する」という拡散のパラドクスをそれまでの常識を単純な数学モデルを用いて説明し、当時の生物現象の中で大きな謎であった形態形成や細胞分化の仕組みはそのパラドクスが引き起こしているではと主張したのです。彼の考えは、必ずしも遺伝子がすべてを命令するという分子生物学が示唆するトップダウンのやり方だけではなく、複数の形態因子の拡散と相互作用の間に適当なバランスがあれば、起こりうるというボトムアップの考えを主張したのです。残念ながら、彼の考えは、当時の生物界ではまったく認められず、机上の空論と片付けられたのでしたが、その考えは数学のみならず、自然科学の中で色褪せることなく発展し、現在では自然科学のみならず、工学、社会科学の分野でも認められるようになって来ました。これは正しく現象数理学の原点であります。
今回の講義において数学から生物学にメッセージを送ったチューリングの考えを現象数理学の視点から諸君に伝えることが出来ればと思っています。
平成21年12月
明治大学理工学部・教授
先端数理科学インスティテュート・所長
三村昌泰