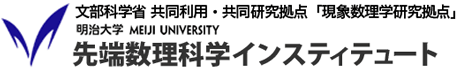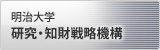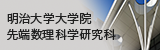オンデマンド配信
オンデマンド動画配信
私立大学研究ブランディング事業 第5回公開シンポジウム
【身の回りの?を数理の目で解き明かす-】
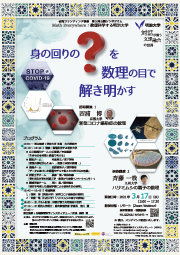
明治大学は、文部科学省平成28年度私立大学研究ブランディング事業に採択された「Math Everywhere:数理科学する明治大学-モデリングによる現象の解明-」の第5回公開シンポジウムを、3月17日(水)にオンラインで開催いたしました。
当日の講演を記録した動画をオンデマンド配信しています。
※ 特別講演1 西浦博教授による講演の配信はありません。
開催日 :2021年3月17日
開催形態:リモート オンラインセミナー (Zoom Webinar)
【配信プログラム】
■ 開会挨拶 明治大学学長 大六野 耕作
Ⅰ. 講演 <数理科学する明治大学>
■自己組織化チーム【生きものを時間と数理で考える】
「生きもの」とは生物のように変化する「もの」と定義してみます。すると、「もの」が示す「生物のような変化」とは何か、という問いが新たに生まれます。生物の?をこの問いから考える数理科学を紹介します。
◆「生きものと自己組織化」
山口智彦:明治大学研究・知財戦略機構 特任教授 自己組織化チームリーダー
◆「『仕組み』を積み上げて実現する高度な機能」
末松信彦:明治大学総合数理学部 教授
■錯視チーム【錯覚の解明から生成へ ~視覚と味覚の数理~】
見ることと味わうことに焦点を合わせてその仕組みを数理モデルで探り、さらにそのモデルから新しい錯覚を人工的に作る方法を開発してきた。視覚では不可能立体の新種の発見、味覚では味ディスプレイの開発に成功した。
◆「錯覚の解明から生成へ ~視覚と味覚の数理~」
杉原厚吉:明治大学研究・知財戦略機構 研究特別教授 錯視チームリーダー
◆「錯覚の解明から生成へ ~視覚と味覚の数理~」
宮下芳明:明治大学総合数理学部 教授 錯視チームサブリーダー
■金融チーム【データに基づいた数理モデルで捉えた日常生活の危機】
私たちの日常生活は金融危機のみならず災害、感染症など多種多様な危機に晒されている。さまざまなデータに基づいた数理モデルの研究および開発で捉えたエビデンスに基づいて、日常生活の危機の本質と今後を探る。
◆「データに基づいた数理モデルで捉えた日常生活の危機」
田野倉葉子:明治大学大学院先端数理科学研究科 准教授 金融チームリーダー
◆「データに基づいた数理モデルで捉えた日常生活の危機」
浅井義裕:明治大学商学部 教授
■ 折紙工学チーム
【畳む文化が育む折紙工学 ~数理から産業イノベーションを!~】
折紙構造の特徴である軽くて強い、展開収縮できるという特徴を活かした最高の傑作がそれぞれで得られたこと、折紙設計から折紙式プリンターへの構想と現状、芸術史上稀な立体芸術である日本発の折畳扇研究を紹介する。
◆「空き箱やペットボトルを平らに折りたたむには?」
奈良知惠:明治大学研究・知財戦略機構 客員研究員 折紙工学チームサブリーダー
◆「畳む文化が育む折紙工学 ~数理から産業イノベーションを!~」
萩原一郎:明治大学研究・知財戦略機構 研究特別教授 折紙工学チームリーダー
■機械学習チーム【感性を考慮した機械学習による快適生活の実現】
人工知能は私達の生活に利便性を与えるが、さらに人の喜びや満足感などの感性を考慮して、快適性を与えることもできる。ここでは、機械学習により人の感性を考慮することができるシステムについて紹介する。
◆「感性を考慮した機械学習による快適生活の実現」
荒川 薫:明治大学総合数理学部長 教授 機械学習チームリーダー
◆「文章から感情を読み取る ~感情分析の数理~」
櫻井義尚:明治大学総合数理学部 教授
Ⅱ. 特別講演 「ハサミムシの扇子の数理」
斉藤一哉:九州大学大学院 芸術工学研究院 講師
ハサミムシは独自に進化した方法で昆虫の中で最もコンパクトに翅を折り畳み収納しています。この講演では折紙の幾何学と最新のデジタル・ファブリケーション技術でこの折り畳みの数理的な謎を解き明かし、人工の展開構造のデザインに応用する研究を紹介します。
Ⅲ. パネル討論 <対話が誘う文理融合の世界>
【モデレーター】
● 西森 拓 明治大学研究・知財戦略機構 特任教授
● 俣野 博 明治大学研究・知財戦略機構 特任教授、MIMS所長
【パネリスト】
■自己組織化チーム 山口智彦,末松信彦
■錯視チーム 杉原厚吉,宮下芳明
■金融チーム 田野倉葉子
■折紙工学チーム 萩原一郎,奈良知惠
■招待講演者 斉藤一哉