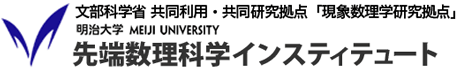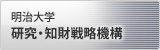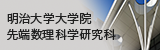高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2021
- ホーム
- セミナー・シンポジウム
- 高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2021
目 的 :
先端数理科学インスティテュート(MIMS)では、2011年から毎年、「高校生による現象数理学研究発表会」を開催してきました。あいにく2019年の第9回は、台風のため直前に中止を余儀なくされ、2020年は新型コロナ感染症の広がりを受けて開催できませんでしたが、2018年の第8回まで全国各地から多くの高校に参加していただき、活気のある研究発表の場を提供することができました。これらの発表会に参加してくださった高校生や高校教師の皆さま、また、このプログラムの開催に協力してくださった関係者の皆さまに、この場を借りて御礼申し上げます。
さて、MIMSでは、今年度から新しいプログラムとして「高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会」を立ち上げることにいたしました。これは、数理的視点を自然や社会の理解に活用する面白さを一流の講師が語る入門講座と、高校生による研究発表会の二部構成になっています。二部構成にすることで、多角的な視点から現象数理学の魅力を伝えることができ、より多くの皆さまに興味をもっていただけると考えております。また、こうした活動を通して、わが国における現象数理学の裾野がさらに広がるよう願っております。発表会に参加しない方も視聴は自由ですので、多くの方々のご参加・ご視聴を歓迎いたします。
MIMS所長 俣野 博
開催概要
開催日 : 2021年10月9日(土)、10日(日)(参加無料)
開催方法 : Zoom社の Webinar 機能を使用したオンラインで開催
本研究会のプログラム :
本研究会は、次の2部構成になります。
・第1部: 現象数理学入門講座
・第2部: 高校生による研究発表会
スケジュール
10月9日(土) 13:50 開会の挨拶と趣旨説明 14:00~14:50 現象数理学入門講座
「現象数理学おもしろ講座 1」
矢崎成俊 (明治大学 理工学部 教授)14:50~15:00 質疑応答 15:00~15:50 現象数理学入門講座
「トポロジーで探る対称性と周期性 1」
河野俊丈 (明治大学 総合数理学部 教授)15:50~16:00 質疑応答
10月10日(日) 10:00~10:50 現象数理学入門講座
「現象数理学おもしろ講座 2」
矢崎成俊 (明治大学 理工学部 教授)10:50~11:00 質疑応答 11:00~11:50 現象数理学入門講座
「トポロジーで探る対称性と周期性 2」
河野俊丈 (明治大学 総合数理学部 教授)11:50~12:00 質疑応答 休憩
13:00~17:00 高校生による研究発表会・表彰式,講評
- MIMS所長挨拶
- 受賞研究の紹介
奨励賞
優秀賞
- 表彰状授与
- 受賞の挨拶
- 受賞者による研究発表
奨励賞2件
優秀賞3件
- 結びの挨拶
◆ 視聴のみの参加も可能です(無料)。 高校生や高校教諭に限らず、どなたでも視聴できます。
第1部:現象数理学入門講座
◆ 講師 : 矢崎成俊 (明治大学理工学部数学科 教授) ◆ 講師 : 河野俊丈 (明治大学総合数理学部現象数理学科 教授) |
※ 数理的視点を自然や社会の理解に活用する面白さを一流の講師が語る入門講座です。
※ それぞれ約50分の講義が2回ずつ行われます。
(講義題目は変更される可能性があります)
【矢崎成俊】 (明治大学理工学部数学科 教授) 「現象数理学おもしろ講座」 |
撮影・河野裕昭 |
講義内容
例えばレシートのような小さな紙片を自分の頭の高さから落とすことを考えてみましょう。紙片はひらひらと複雑な動きをしながら落下するので、何秒後に地面に落ちるかを正確に予測することは困難です。
しかし、紙片の代わりにテニスボールだったら、かなり高い精度で落下時間と落下地点を予測することができるでしょう。
この違いは何でしょうか?逆に考えると、紙片の行方を正確に予測するにはどんな条件が必要でしょうか?
ぼくらの身の回りには、見慣れているけどよくよく考えると不思議で面白い現象が沢山あります。また、感染症流行や地震、温暖化など、解決の難しい問題も沢山あります。これらの現象は、なぜ正確に予測することが難しいのか、そしてそのような現象を扱うためには、どのように観察し、理解していけばいいのか、そのヒントとなる見方や考え方を、簡単な実験などを交えながら紹介します。

【河野俊丈】
(明治大学総合数理学部現象数理学科 教授)
「トポロジーで探る対称性と周期性」
講義内容
私たちのまわりには、様々な規則的なパターンが存在します。原子や分子などの配置、植物の葉の配列などはそのようなパターンの例です。
このような規則性について対称性をキーワードにして記述することを考えます。2つの方向の平行移動で変わらないような対称性のパターンは平面結晶群によって記述されますが、これをトポロジーの考え方を用いて分類することを説明します。さらに、周期性を持たないタイル貼りについても扱います。
第2部:高校生による研究発表会
高校生による現象数理学に関する研究を募集します。応募内容を審査し、優れた研究を複数表彰します。
2021年度の募集は終了しました。
2021年度の募集概要(参考)>>>
◆ 2021年度 高校生による研究発表会の受賞者が決定しました。
[俣野博MIMS所長のコメント]
今回の応募研究の中には意欲的で水準の高い研究が数多くあり、審査員も驚くほどでした。これらの若い才能を、今後もしっかり伸ばしていってほしいと思います。
【高校生による研究発表会2021 受賞者】
| 【優秀賞】 | |
筑波大学附属駒場高等学校 「円形会議場での効率的かつ安全な会議方法」 |
|
広島大学附属高等学校 「Buffon’s leaf problem」 |
|
広尾学園高等学校 「塾生数の動向予測 -SIR モデルとヒット現象モデルを用いたシミュレーション-」 |
|
| 【奨励賞】 | |
広尾学園高等学校 「実現可能な錯視立体の作成」 |
|
広尾学園高等学校 「待ち行列理論を用いたエスカレーターの乗り方の評価」 |
|
|
|
問い合わせ先
明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)
〒164-8525
東京都中野区中野4−21−1
明治大学中野キャンパス 高層棟8階
TEL : 03-5343-8067 (月~金の平日 9:30~16:00)
E-mail:mims.cmma.meiji [at] gmail.com
※メールアドレスの[at]を @に変更してください。
主 催
明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)
- 本研究会は、MIMSが運営する文部科学省共同利用・共同研究拠点 明治大学「現象数理学研究拠点」の活動の一環として開催します。文部科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」JPMXP0620335886の助成を受けています。